コラム・対談 Columns
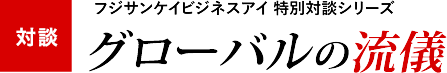
グローバルの流儀 フジサンケイビジネスアイ紙 特別対談シリーズ『グローバルの流儀』は、弊社代表の森辺がグローバルで活躍する企業の経営トップにインタビューし、その企業のグローバル市場における成功の原動力がどこにあるのか、主要な成功要因(KSF)は何かなど、その企業の魅力に迫る企画です。本企画は2015年にスタートし、今年で11年目を迎えます。インタビュー記事は、新聞及び、ネットに掲載されています。
Vol.18 日本人なら誰もが知る「マルコメの“味噌”」を「世界の“MISO”」へ
マルコメ株式会社 海外事業本部 執行役員 伏見 和彦 氏
現場の意見が生きる「自律分散型組織」がマーケティングの強さの秘訣
森辺: 御社は1854年に味噌、醤油醸造業を開始し、1948年に青木味噌醤油株式会社を設立。 1967年に社名をマルコメ味噌株式会社に、1990年にマルコメ株式会社に改称されていますね。 御社の取扱い商品の変遷について教えていただけますでしょうか。
伏見: 「マルコメ」というと、「マルコメみそ」を思い浮かべてくださる方が多いでしょう。当社は本社を長野に置く信州みその会社です。
1978年、当社は業界トップに躍進しました。 当時は日本人1人当たりのみその消費量は年間4.2kg強あったものの、平成の時代に入ると次第に減少し、現在では2kg強と、ほぼ半減しています。 「我が家は毎日和食です」というご家庭は、今では希少な存在でしょう。 そんな中、当社のここ10年間の売上は約1.5倍に増えています。 それは、みそだけにとどまらず、米みそに欠かせない米糀から作る糀甘酒を始めとする糀関連、 同じくみその主原料である大豆から作る大豆のお肉、大豆ミートを第2、第3の事業として確立してきたからに他なりません。 特に食のニーズとしてエコ、サスティナブルというものがあり、フェイクミートは海外でも人気が上昇、マーケットが拡大しています。 そうした背景もあって、今、国内でも大豆ミートにメディアが注目しているんです。
また、小麦粉を使わないグルテンフリーの需要から、近年、大豆粉の売上も伸びてきています。
森辺: 御社はみその売上が国内NO.1の日本を代表するみそメーカーです。業界トップに君臨し続けている成功要因は一体何だとお考えですか?

伏見: まず言えるのは、既存商品でありながら新しい市場を作り出すという商品開発力でしょう。 例えば、みそはみそでも、2009年、業界に先駆けて液状タイプのみそを発売しました。 これが特に宣伝をしていなくても右肩上がりに増えています。 生みそは横ばいなんですが、液みそはずっと伸びているんですよ。 生みそを使って鍋でみそ汁を作る時に、1人分だけ作る人はあまりいないでしょう。 それが、おばあちゃんだけ和食で子どもはパン、なんていう朝ごはんに、液みそならお椀に直接大さじ1杯入れて、好みの具材とお湯で作れるわけです。
大豆ミートにしても、かつては乾燥タイプで湯戻しという手間がかかるものでしたが、 当社は2015年、業界で初めて湯戻し不要のレトルトタイプの大豆ミートを開発しました。

森辺: 他にも御社のヒット商品には「だし入りみそ」や「丸の内タニタ食堂の減塩みそ」などがありますよね。 日本のみそ市場が下り坂になる中、御社はみそのイノベーションで売上を高めてきているわけですね。 このような固定概念にとらわれることのない商品開発を進められるのは、御社はマーケティング力も長けているのではないかと思うんですが。
伏見: 売れる商品を作るところがマーケティングのスタートです。 そのためには商品開発の部署とマーケティングの部署が一体になっていなければなりません。 その点、当社ではマーケティング本部の中に開発、商品企画、営業、宣伝がある。 だから、現場の意見を商品開発にどんどん取り入れることができるんです。 入社1年目の社員であってもそこに参加できるわけですから、第三者的かつ新鮮なアイディアを生かしやすいといえるでしょう。 当社は400人ちょっとの中小企業ですから、組織が小さいからこそできることかもしれませんが。
2019年の「全国発酵食品サミット in Nagano」で「第1回長野県甘酒鑑評会」が行われ、当社は長野県知事賞に選ばれました。 その表彰式で、他社からは中高年のベテラン開発者が居並ぶ中、当社からは入社2年目の女性社員が出席。 彼女が開発の中心者だったからに他なりません。
森辺: すごいですね、それは。ほとんどのメーカーでは、生産や開発が企業経営の真ん中にあるものですが、マーケティングの下に開発や生産がある。 そういう環境にあるというのが御社の強みなのかもしれないですね。
伏見: 下というか、開発も営業も広報や商品企画も、全部同じチームとして動いているという感じです。 当社は青木家のオーナー会社で、昔は会長や社長がある程度新商品の開発に携わりながら最終決断をするというのが定番でした。 いわゆるカリスマ経営者ですね。それが現社長に代わってから、マーケティングと社長は横並びのような環境です。 社長は商品開発には一切口出しをしませんね。
当社では社員一人一人が会社の発展や改革に必要な力をつけるエンパワーメントの考え方を大切にしています。 社員が自律的に機能する自律分散型の組織だといえるでしょう。 オーナー会社というとネガティブなイメージを持たれてる方もいると思いますが、当社にはオーナー会社にありがちなデメリットは見当たりません。 一方で、オーナー判断で思い切った投資ができるのはメリットのひとつ。 2019年で創業165年になる当社ですが、老舗の皮を被ったベンチャーのような動き方をしています。
生活者のニーズを顕在化し、「ギルトフリー」の流れに乗って躍進
森辺: 御社はその昔、マルコメ君のCMで一世を風靡しました。 近年はミランダ・カーの起用や独自でアニメCMを制作するなど、プロモーション戦略が一新しています。 これらの取り組みについてお聞かせいただけますでしょうか。

伏見: マルコメ君のCMは、30代半ば以降の方の認知度は高いでしょう。ただ、そのイメージが強過ぎたというデメリットもあります。 今の当社はマルコメみそだけではなく、糀甘酒や大豆ミートでも「マルコメ!」と思っていただきたいんですよね。 かつてのイメージとはまた違ったマルコメ色というものを、今作ろうとしている最中です。
森辺: その違ったマルコメ色を出すための、今後の展望についてお聞かせください。
伏見: 発酵食品といえばマルコメ、ということで、さまざまな企画でお声がかかります。 ありがたいことですが、発酵食品の枠を超えた打ち出し方をしていきたい。
当社が今、お世話になっている大豆ミート料理研究家の坂東先生という女性の方がいて、この方が無類の肉好きなんですよ。 つまり、もはや大豆ミートはビーガンやベジタリアンのためだけのものじゃない。 最近食べ過ぎているという自覚のある方が、食堂にカツカレーと大豆ミートのキーマカレーがあったら、 大豆ミートを選ぶ可能性は大いにあります。 この罪悪感のない食事を意味する「ギルトフリー」というニーズは昔からあったものの、 近年、このワードのお陰で見える化されてきました。 メディアで特集が組まれることも増えてきましたね。 当社の商品は発酵食品にグルテンフリーの大豆ミートや大豆粉と、全てギルトフリーに属するので、 いい流れが来ていると感じています。
だからこそ、ギルトフリーの認識を高めるとともに、もっとニーズにお応えし得るような商品開発に取り組んでいきたいですね。 例えば当社の糀甘酒を使えば、砂糖やみりんを入れなくても、鶏の照り焼きや肉じゃがなどの料理が美味しく作れます。 これもギルトフリーのニーズに応えているんですよね。これからのマーケットだと思います。

森辺: みそは少子高齢化によって消費量は減る一方であるものの、他の商品が伸びている。 そのきっかけがギルトフリーで、御社にはその価値観の商品がたくさんあり、恐らく今後も市場が伸びていくと考えられるわけですね。
伏見: 主力のみそについても、2019年の春夏商品で8種類目の液みそが出るんですよ。 これまでの生みそとの一番の違いは、生みそを1カップ買ったら2週間から1カ月は使い続けるご家庭が多いでしょう。 冷蔵庫のドアポケットに収まる液みそだと、2、3本ストックできる。 昨日は定番のかつおと昆布だしの料亭の味、今日は手巻き寿司だから赤だし……と、その日の献立に合わせて選べるわけです。 この商品力により、液みそはずっと右肩上がりで伸び続けています。20年後のみそ売場の景色はすっかり変わっているでしょうね。
世界45を超える国と地域に、みそ市場の創出から事業を展開
森辺: 御社は2007年に海外生産拠点の先駆けとしてロサンゼルス工場を完成させましたね。 海外では最初にアメリカで事業展開した背景には、 やはりロサンゼルスを中心とした日系、アジア系のマーケットをまず取りにいこうという戦略があるんでしょうか?

伏見: 2004年に当社初の海外向けの部署として、国内組織の中で国際チームという新設部署ができました。 当時の年間輸出量は本社工場の1日の出荷にも満たないくらいでしたが、 国際チームを作った背景には、国内市場が縮小していく中で海外進出は避けられないという社長判断があったんです。 中国やアジア、アメリカに、まずは海外拠点を作り、現地の生活者のニーズや嗜好を肌身に感じて進んでいこうという戦略。 私も2004年にアメリカを北から南下して、いろいろなメーカーの工場を視察して回りました。 その結果、日本からの輸出量が最大であり、日本食レストランが当時5万店近くになろうとしていたアメリカで打って出ようと。 同業他社がアメリカで事業展開を始めていたことを意識した部分もあったかもしれないですね。最終的に工場まで作ることになりました。
森辺: アメリカが一番大きいマーケットになっているということですね。 御社は既に45カ国に展開をしていて、アメリカに工場を持っている他にも、英国、韓国、タイには現地法人を構えていますね。 現産現販しているところ、現地で販売会社を持って販売をしているところ、そして日本から輸出をしているところと、3つの形態があるわけです。 それぞれどういう状況なのかを教えていただけますか?
伏見: 現産現販をしているアメリカでは、自分たちで作ってお客様に手渡していくという流れを肌身に感じ、全ての情報が直接入ってくるという利点があります。 販売会社を持っているところでは、生活者がどんな感覚でみそ汁を飲んでいるのかを把握した上で、それに応じた営業活動ができることがメリットでしょう。 この2つの形態は、我々の企業理念である「日本古来の発酵技術を通じて生活者の健やかな暮らしに貢献する」ことにつながっています。
また輸出では、なかなか我々の手が届かない部分を海外のディストリビューターさんに任せることにより、市場シェアを取るという意識が強いですね。

森辺: 日本の問屋さんを通じて輸出をするだけというのが、海外展開のパターンとしてよくあります。 全く生活者の顔が見えていないので、その商品がどういう中間流通を通じて、どういう小売にどう並べられて、 どんなSKU取りをして、どんな生活者がそれを買って何を思ってリピートしているのか、していないのかを全く無視している。 これではグローバルビジネスとはいえません。 最初はこのパターンで始まったとしても、日本から輸出した商品を現地でコントロールして売っていくというパターンに変化していくのがベストですよね。
従来の生活者の顔が見えない輸出ビジネスでは、毎年105%成長はしても劇的な成長はしません。 アジア新興国でいうと、近代小売には並ぶものの、伝統小売には並ばない。 これでは本当の意味でのローカルの生活者の食べもの、飲みものにはならない、という問題を抱えています。 みそという商材を現地の人が食べるようなものにするには、現地の食事にそれをどう使わせるのか、 どう食すのかということを教育をしていく必要があるので、すごくハードルの高いビジネスだという気がするんですが。
伏見: 本当に国によって環境が全然違うので、そこに合わせた戦略を練らないといけません。 韓国の場合はテンジャンという、同じようなみその文化がある。 だけど、若い世代は嗜好が変わってきていて、テンジャンがしょっぱ過ぎる、辛過ぎるといって敬遠するような傾向があります。 これはものすごいチャンスで、日本のみそがマイルドでいいと受け入れられる可能性がある。 韓国人の生活者とコミュニケーションを取ってみると、親が子どもに何とか食べてもらおうと、 テンジャンと日本のみそをブレンドしている、などという情報がキャッチできます。 こうした情報を受けて、販路を変えるなどという新たな戦略が見えてくるんですよ。
国際チームの発足当初は、ちょっと辛いキムチテイストのみそを発想したものですが、これは大間違い。 アメリカで工場を作りながらレストランに配荷していく中で、だんだん気付き始めました。 彼らは日本のものを求めているんですよ。 ある程度、現地に合わせることは必要ですが、 基本的にメーカーが「この国に合わせました」というものは絶対に受け入れられないと、つくづく感じています。
森辺: そうすると、日本で日本人が食している味を求めている現地の人をターゲットにしているということになりますか?
伏見: 今、ユネスコ無形文化遺産に登録された和食に注目が集まっていて、各国ともに和食レストランが増加しているという事実があることに加え、 ヘルシーフード志向の高まりというのも全世界的にあります。 日本の伝統調味料であるみそは、まさにヘルシーフードのど真ん中といえるでしょう。 それを、現地に合わせた販売戦略を立てて、お客様が買いやすい環境を提供することで気軽に手にしていただく。 それによって当社の現地市場シェアも上がっていくと考えています。
日本食レストランが引き続き増え続けるとは思いますが、いきなり生みそを使ってもらうのは難しい。 入口としてインスタントみそ汁があったりするわけなので、その段階を海外の方に踏んでいただくためには、 インスタントみそ汁を配荷する必要があります。 それから、みそというものをもっと知ってもらわなければならない。 その奥には発酵食品が健康につながるということを伝える使命もあるということですね。
日本食レストランや寿司バーで、ボタンをカチッと押すと自動で1杯ずつみそ汁が抽出されるサーバー、ディスペンサーがありますよね。 当社もそのような業務用のみそ汁を展開しています。 適量のみそと適量のお湯でおいしいみそ汁が簡単にできるのは、インスタントであってもみそ汁の啓蒙に一役買っていると考えているんですよ。 業務用インスタントみそ汁は海外における当社の主要商品だといえますね。
森辺: 生活者の市場は業務用が進むにつれて伸びていくケースが多いので、これからがチャンスですね。
伏見: ただ、それだけではダメだという考えから変化が現れてきています。 我々がレストランチェーンの本部に出向いて、さまざまな風味の液みそや大豆ミート、糀甘酒をアピールするような営業活動も行っているんですよ。 BtoBでもBtoCでも、直接お客様とコミュニケーションを取ることが大切だと感じています。 森辺さんが先ほどおっしゃっていた「消費者の顔が見えない輸出ビジネス」には、当社は当てはまらないといえるでしょう。 45カ国へ輸出された先のことを我々はきちんと把握しているという自負があります。
醤油、酢、化学調味料の先駆者に追随し、みそ業界を牽引する存在に
森辺: 国内のみそ市場において、イノベーションで売上アップを達成してきた御社ですが、 食品や飲料系の業界は今後、海外に力を入れなければ上っていきにくいと思います。 今後の御社のグローバル戦略をお聞きできますでしょうか。
伏見: 輸出量が増えているとはいえ、みそ全体を他の調味料をはじめとする食品と比べると、まだまだ小さいんです。 みそ自体も、当然マルコメという会社も知らない人がほとんど。 以前はシェアを拡大しよう、他の同業他社に勝とう、という思いがありましたが、 今は我々が市場を作る、創出する、というのが共通理念になっています。 現地法人に関しては、本社機能からいろいろな権限を移譲していて、大きな判断は本社で下しますが、 それ以外の判断はそれぞれの現地法人に任せ、そこで動きやすいように動くようにしているんですよ。

森辺: 海外展開を行う企業のほとんどは何かしらの課題を抱えていて、 この課題をどれだけ早く確実にクリアをしていくかがグローバル競争の大きなポイントになると思います。 御社の場合、海外展開における課題や難しさを感じるのはどのような点でしょうか。
伏見: 課題はズバリ、グローバル人材の採用と育成ですね。 今、国内にある人材を育成するにはある程度の時間を要します。 また、社内的にもグローバル化がもう少し進んでいけば、新人のグローバル社員を育てるという余裕もできるでしょう。 あとは現地で採用するパターンもありますが、これもなかなか難しい。 まだ海外展開が初期段階である今の当社のレベルでは、適した人材を他社から引き抜くというのが最善策ではないかと考えています。
森辺: 最後に、御社の今後の長期的なグローバル市場における展望についてお聞かせいただけますでしょうか。
伏見: みそ、糀、大豆事業を国内と同様に海外でも3本柱として大きな市場を取っていく、成長していくということは共通認識です。 海外における基礎調味料市場の中では、みそ業界が非常に出遅れているというのが周知の事実。 醤油のキッコーマンさん、酢のミツカンさん、うま味調味料の味の素さんを見ると、売上の半分以上が海外です。 当社がみそ業界を牽引して、大いに盛り上げていきたいですね。
ゲスト

伏見 和彦 (ふしみ かずひこ) 氏
マルコメ株式会社 海外事業本部 執行役員
Kazuhiko Fushimi, marukome
1983年、マルコメ味噌株式会社(現、マルコメ株式会社)に入社。千葉営業所勤務を経て東京支店に異動、大手GMSの本部担当に従事。2004年よりマルコメ初の海外担当部署として新設された国際チームを兼任。2007年に現地法人のMarukome U.S.A.,Inc.へ営業マネージャーとして出向。同年12月にMarukome U.S.A.,Inc.工場が竣工、アメリカ産味噌の営業を開始。2011年に帰国、タイランドと韓国の現地法人設立に向けた準備期間を経て2013年に開設。現在は海外事業本部執行役員として、アジア・オーストラリアを中心に海外事業課と現地法人を統括している。
インタビュアー

森辺 一樹(もりべ かずき)
スパイダー・イニシアティブ株式会社 代表取締役社長
法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科 特任講師
Kazuki Moribe, SPYDER INITIATIVE
1974年生まれ。幼少期をシンガポールで過ごす。アメリカン・スクール卒。帰国後、法政大学経営学部を卒業し、大手医療機器メーカーに入社。2002年、中国・香港にて、新興国に特化した市場調査会社を創業し代表取締役社長に就任。2013年、市場調査会社を売却し、日本企業の海外販路構築を支援するスパイダー・イニシアティブ株式会社を設立。専門はグローバル・マーケティング。海外販路構築を強みとし、市場参入戦略やチャネル構築の支援を得意とする。大手を中心に17年で1,000社以上の新興国展開の支援実績を持つ。著書に、『「アジアで儲かる会社」に変わる30の方法』中経出版[KADOKAWA])、『わかりやすい現地に寄り添うアジアビジネスの教科書』白桃書房)などがある。


